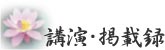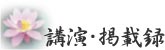「今を生きる」第66回 大分合同新聞 平成19年2月12日(月)朝刊 文化欄掲載
天人五衰(2)
前回の天人五衰を解説します。
頭上華萎(ずじょうかい)…頭上の華がしぼむ。頭にかざった華が萎(しお)れていく、黒髪を誇っていた者にも白髪が混じるようになったり、頭髪が弱ったり、抜けたりして薄くなっていくさまをいっています。
人の目を楽しませる切り花も時間がたつと必ず萎れる。盛んなることを誇る者も必ず衰える、その法則を免れることはできないのです。世俗世界での願い事成就は次なる悩みの種になるという迷いの世界を超えてないということです。
かつて、わが家の子どもたちが大学生のとき、帰省するたびに髪の毛の色が変わることに戸惑いを覚えたことがあります。若さだけで十分に輝いているのにもったいないことをすると感じていました。
人が老化していくと、以前だと頭や顔が老化してもすぐあきらめがついていましたが、髪を染めることが簡単にでき、男性でも化粧するようになると、自分の老化の現実をなかなかあきらめられず、いつまでも心が落ち着かない。 しかし、不自然なあり方を続けていくと必ず自然なあり方に戻されていく、どこかで化けの皮が剥(は)がされるのです。
マスコミに登場する芸能人や政治家の中で、若く元気に見せる為のご苦労が痛ましく思われることがあります。流れに逆らって頑張るのを「努力」といい、流れに逆らわずに頑張るのを「精進」というそうですが。自分の素肌でない仮面の状態で誉められても、それは本心から嬉しいことにならないでしょう。
外面的な見栄えより内面的な充実、「よい大人に、よい年寄りになろう」と人間的に精進して成熟し、心豊かな人生を歩むことを仏教は教えてくれています。
田畑正久(たばた まさひさ)
1949年、大分県宇佐市の生まれ。九大病院、国立中津病院を経て東国東広域病院へ、同院長を10年間勤め2004年の3月勇退。現在宇佐市の佐藤第二病院に医師として勤務、飯田女子短大客員教授として医療と仏教の協力関係構築に取り組んでいる。 |